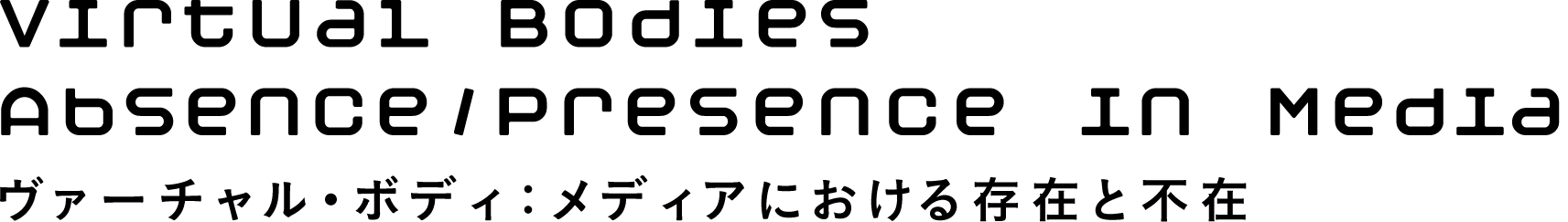(アルファベット順)
アーティスト

生物学的な観点から自身を「バクテリア・コミュニティ」と称している。「生態系の危機」と呼ばれる現代において、異なる生物間の共生に注目し、嗅覚やオブジェを用いて表現を通そし、研究している。今回の展覧会では、ゼハーズは「filthglycerin(フィルスグリセリン)」(2017年)を公開。本作ではグリセリン液体石鹸と、犬の唾液や毛などの発酵した有機的な要素が対照的に組み合わせられ、西洋における植民地時代の生物医学と衛生学のシステムに対する批判が暗示される。また、今回はアルコールジェルを浸漬液として使用することにより、ポストコロナ時代を反映した作品となっている。

2010年に制作を開始した「Pinturas de interfaz(インターフェース・ペインティング)」のシリーズでは、ウェブ・インターフェースを油絵に変換することによって、新しいメディアを質感と記号論によって解体し、メディアを置き換えることを試みた。本展ではメディアとテクノロジーの観点から、社会やジェンダーが形作るアイデンティティについて、サン・マルティンによる長年の考察を表す「Zoom, n°1」を公開。本作はトロピカルな色彩のフェルトと再利用された布を用いて、コロナ禍で多用されているZoom通話画面の輪郭を再現し、時間・仕事・人との関わりを再解釈するテキスタイル作品である。

本展では、日本語で「電子の仮面」を意味する「Mascara electrónica」(マスカラ・エレクトロニカ)を発表する。本作は今日のデジタル化された消費文化と、先コロンブス期のメキシコ美術に見られる精巧なマスクの、両方からインスピレーションを受け、廃棄された電子機器のマイクロチップボードが美容マスクの形に仕立てられている。本作は、私たちが常にデジタル・アバターの仮面をつけているかのような不気味さを感じさせ、デジタルメディアがいかに私たちの自己認識やアイデンティティに影響するのかを問いかける。

本展で発表する「ノーティフィケーションズ」(2021年)は、新型コロナウイルスの世界的な流行により、他者とのソーシャルディスタンスを余儀なくされた状況の中で制作された。デジタル・レンダリングと映像を組み合わせた本作では、コロナ禍におけるテクノロジーの普及に対して警戒を示す言説に、異議を唱える。というのも近藤自身が身体障害者として、移動やコミュニケーションを始めとする日常的行為において、長年テクノロジーに依存してきたからである。
「クィアストリートTUA」(2017年)は、本展の会場周辺の上野公園で、1948年に政府により弾圧を受けていた男娼たちの運動という歴史的瞬間を探求する。雨の降る公園という仮想的な場面に、クィア・コミュニティによる政治と表現に関するスローガンが現在の建物に映し出され、地域における不可解なクィアの歴史が浮かび上がる。
「マルティプル・アイデンティティズ」は、人型のモデルと表面に印刷された容姿のラベルとが一致しない彫刻作品で、近藤の作品に一貫している「単一アイデンティティのクィア化」というテーマが見られる。
注1―Robert McRuer『Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability』(2006, NYU Press)。

本作では、Googleマップのストリートビューモードを使って、アメリカ・ユタ州のスキー場にやってきた。すると空にどこか愛嬌があり、考えさせられるような、折れた赤い旗が現れた。そこで、パソコンの画面上で構図を定めてスクリーンショットを撮り、デジタルカメラでパソコンの画面上の途切れた旗のイメージを再び撮影して、そのイメージのネガを『1984』という小説のページにスケッチした。さらに、8×10インチのモノクロネガフィルムで絵画のネガフィルム版を再現し、「ポジネガ」を得た。最後にネガフィルムをプラチナ技法で印画紙に仕上げた。
本展では、Googleストリートビューのスクリーンショット、コンピュータ画面のストリートビュー写真のリメイク、スケッチ、8×10インチのモノクロネガフィルム、プラチナクラフト写真を展示。

本展で展示されるインスタレーション「Platform Ghosts(プラットフォーム・ゴースト)」は、シルヴィオ・ロルッソとセバスチャン・シュメーグによる共同作である。本作の大部分は、スマートフィルムの施された透明なパネルによって構成される。そレラのパネルは鮮やかな紫色に染まり、テクノロジーを介した人間関係や内省を思わせる言葉が表示される。しかし鑑賞者が近づくと、それらの文字は徐々に薄れ、やがて完全に透明な状態に戻る。本作は、デジタル・プラットフォームに見られる表現の政治性や情緒作用について、幽霊というメタファーによって考察することを促し、自動化の進んだ「スマートシティ」に住む私たちの未来について想像させる。

本展で展示されるインスタレーション「Platform Ghosts(プラットフォーム・ゴースト)」は、シルヴィオ・ロルッソとセバスチャン・シュメーグによる共同作である。本作の大部分は、スマートフィルムの施された透明なパネルによって構成される。そレラのパネルは鮮やかな紫色に染まり、テクノロジーを介した人間関係や内省を思わせる言葉が表示される。しかし鑑賞者が近づくと、それらの文字は徐々に薄れ、やがて完全に透明な状態に戻る。本作は、デジタル・プラットフォームに見られる表現の政治性や情緒作用について、幽霊というメタファーによって考察することを促し、自動化の進んだ「スマートシティ」に住む私たちの未来について想像させる。

本展では「Headlines(ヘッドラインズ)」(2020年)シリーズというネット・アートと映像インスタレーションのプロジェクトから1点を展示する。世界的なパンデミックが始まった2020年に制作され、常に進化し続ける本シリーズは、主流メディアに見られるフェイクニュースの流布や人道危機が叫ばれる一方、コロナウイルスの経済的影響について報道機関が大きく取り上げている実態を分析する。本作は今回の展示に向けて、特別にカスタマイズされた壁紙とデジタル映像のインスタレーションとして展開される。


撮影を通じて、人と人の距離、人と空間のつながり、人と環境と物との関係に注目する。本展では、写真のインスタレーション「動物園を見てまわるのは真面目なことだ」(2020年)とミクストメディア・インスタレーション「野毛山幻像」(2021年)を公開。これらの2作において、魏は見ることと見られることという対立する視点や、人間の不在及び存在について探求し、人間中心主義的な観点による人と動物の関係について批判的な眼差しを向ける。

本展では「メメント・モモ」(2019 - 2022)というプロジェクト型作品を初公開。本プロジェクトは、ミヒャエル・エンデの小説に登場する「モモ」という主人公と同じ名前の雌豚を飼育し、自らの手で屠殺するまでのプロセスを記録する様々なドキュメンテーションから成り立つ。八島は異なる生の体に触れ、時間を共にした不思議で過酷な体験をインスタレーションとして提示する。

本展では、アーティストによる初の長編ドキュメンタリー映画「画像:三人の女性」(2010年)を上映します。章は大学卒業後に母と祖母と生活を共にし、自らの過去と繋がりたいと願う一方、伝統的な価値観から自由になりたいという強い想いのあいだで葛藤を繰り返してきた。本作では母親と祖母との間接的な対話やモノローグ、日常生活の場面を、詩的なダンス・パフォーマンスと重ねる。ダンサーを演じる章は、電子スキャナーやデジタル投影といったテクノロジカルな手法を用いて、母親や祖母とのインタビューを自らの体に映し出す。本展では「自画像:私と母の対話」(2009年)の短編ドキュメンタリーも併せて紹介し、「3人の女性による自画像」に向けてのリサーチや実験的な表現を公開する。

本展では「シダ性愛」映画プロジェクトの第4部を公開。本プロジェクトは人間と植物種、特にシダとの種間関係について、身体的及び視覚的に探求する。東アジアの男性が植物と身体的に触れ合うエコセクシャルなパフォーマンスを通じて、クィアな欲望という概念を表現することを試みる。第1部は2016年に初公開され、続くあとの2部は2018年、コロナ禍の前に上演された。人間と自然、さらに体との関係が変化している今日、鄭による本作は新しくオルタナティブな視座を提示する。